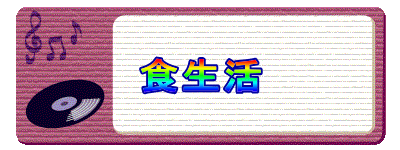
|
NO, |
大分類 |
中分類 |
名称 |
写真 |
解説 |
展示場所・備考 |
|
1 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
セエロ (蒸籠) |
|
もち米や饅頭などをふかすための道具で、湯を沸かした大釜の上に置き、その湯気でふかす。 円形と方形とがあり、数段を重ねて使う。 |
1階展示室 |
|
2 |
食生活
|
食料調製用具 |
臼と杵 |
|
これは餅搗き用であるが、他に穀物を搗くものもある。 後者は小さな穀粒が外に飛び出ないように縁部がすぼまっており、中央には穀物の粒が回転するように搗き輪を入れる。味噌豆を搗くにも用いられる。 |
1階展示室 |
|
3 |
食生活
|
食料調製用具 |
立ち臼と たて杵 |
|
穀物や餅、味噌豆などを搗く。一本の棒を丸く削り、中央部を握りやすく細く作ってある。 手で握って垂直に打ち下ろす。 さほど体力のない女性や子供でも扱える。 |
1階展示室 |
|
4 |
食生活
|
食料調製用具 |
餅搗き機 |
|
蒸したもち米を電動でこねて餅を作る機械。 |
1階展示室 |
|
5 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
水がめ |
|
井戸水や湧き水を桶に汲んで運び入れ、ひしゃくで汲み飲料水や炊事に用いた。
|
1階展示室 |
|
6 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
すり鉢と すりこぎ |
|
いったゴマ、大豆や味噌などをすったり、魚のすり身を作るのに用いる。 |
1階展示室 |
|
7 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
こね鉢 |
|
トチやケヤキの木をくり抜いた鉢で、うどんやそば、団子を作るとき、粉に水を加えてよくこねるのに使う。 |
1階展示室 |
|
8 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
のし板と 麺棒 |
|
こねたうどん粉やそば粉をのす台。 両手を使って麺棒を回転させながら薄くのしていく。 |
1階展示室 |
|
9 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
茹で上げザル |
|
大釜にはめて、一度に大量のうどんをゆで上げるのに用いた。 ザルごと引き上げて水で晒す。 人寄せ時の必需品とされた。 |
1階展示室 |
|
10 |
食生活 |
炊事・調理用具 |
切りだめ |
|
ゆで上がったうどんやそばをそろえて置き、水切りする容器。 |
1階展示室 |
|
11 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
揚げザル |
|
ゆであがったうどんやそばをボッチにして並べ、食事時にだす容器。 所沢市域では、カブセまたはマツウラと呼ぶこともある。 |
1階展示室 |
|
12 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
まな板 |
|
包丁で食べ物を切るのに用いた台。 始まりは魚を調理するのに使ったのでまな板(真肴板)という。 |
1階展示室 |
|
13 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
カギッツルシ |
|
囲炉裏の上から吊るし、鍋や薬缶、鉄瓶をかける道具。 |
1階展示室 |
|
14 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
ホウロク(焙烙) |
|
ゴマや豆をいったり、ヤキモチ(焼き餅)を作ったりする鉄製の浅い鍋。 古くは素焼きであった。 |
1階展示室 |
|
15 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
鍋 |
|
食物を煮炊きするのに用いる鋳物の鍋で、弦を囲炉裏のカギッツルシ(自在鉤)から下げて使うこともできる。 |
1階展示室 |
|
16 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
片口 |
|
一方に注ぎ口がついた陶製の容器で、酒、酢、醤油などを他の容器に移す時に使う。 |
1階展示室 |
|
17 |
食生活
|
炊事・調理用具 |
釜 |
|
かつては炊飯には、かまどで火を燃やし、釜をかけた。 胴回りに鍔(つば)がついていて火力を拡散させ、すすを防ぎ、吹きこぼれないようにする構造になっている。 |
1階展示室 |
|
18 |
食生活
|
飲食・保存用具 |
御櫃 (おひつ) |
|
炊きあげたご飯を移し入れる木製の蓋つき桶。水気を吸収し、ご飯をうまく仕上げ、ある程度保温もできる。 オハチと呼ぶことが多い。 |
1階展示室 |
|
19 |
食生活
|
飲食・保存用具 |
御櫃入れ(おひついれ) |
|
稲わらや蒲で編んだ蓋付きの籠で、寒期などにご飯を入れた御櫃(おひつ)を包んで保温する道具。 |
1階展示室 |
|
20 |
食生活用具 |
保存・加工用具 |
漬物甕 (つけものがめ) |
|
陶製の甕。梅干を漬けるのに用いられた。 |
1階展示室 |
|
21 |
食生活用具 |
保存・加工用具 |
焼酎甕 (しょうちゅうがめ) |
|
焼酎の容器であるが、空いたものをラッキョウ漬けに転用した。 |
1階展示室 |
|
22 |
食生活
|
保存用具 |
味噌樽 |
|
味噌を入れて販売した陶製の樽で、醸造所の商標が染め付られている。
|
1階展示室 |
|
23 |
食生活
|
保存用具 |
ショイダル(醤油樽) |
|
醤油を入れて保存する道具で、必要な量は栓を緩めて使いやすい容器に移す。 |
1階展示室 |
|
24 |
食生活
|
醸造用具 |
大杓子 |
|
味噌を仕込む時に、煮た大豆と麹と煮汁を四斗樽に入れ、かき混ぜるのに用いる。 |
1階展示室 |
|
25 |
食生活
|
飲食用具 |
箱膳 |
|
一人用の食卓で、箱の蓋を裏返して茶碗、汁椀、小皿、箸、湯飲み茶わんを置いて、食事をした。 食後は、それらの食器にお茶をそそいで飲み干し、箱に納める。 |
1階展示室
|
|
26 |
食生活
|
飲食用具 |
ちゃぶだい |
|
折り畳み式の食卓。 大正から昭和時代に箱膳に代わって普及し、家族そろって一つの食卓を囲んで食事をする形となった。 |
1階展示室
|
|
27 |
食生活
|
管理用具 |
氷冷蔵庫 |
|
食品などを、冷温で貯蔵する木箱。 これは電気でなく、氷屋から氷を運んでもらい、上部の金属張りの室に置き、下に食品を入れて氷の冷気で冷やした。 数日ごとに氷を補給しなければならないので、維持費がかかった。 |
1階展示室 |
|
28 |
食生活 |
嗜好品用具 |
涼炉 |
|
煎茶道に用いる陶製の炉。 炭火を入れて釜を掛け、茶の湯を沸かす。 焜炉、茶炉、風炉ともいう。 |
1階展示室 |